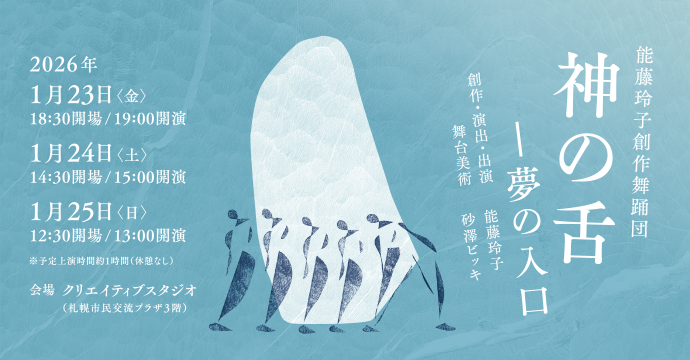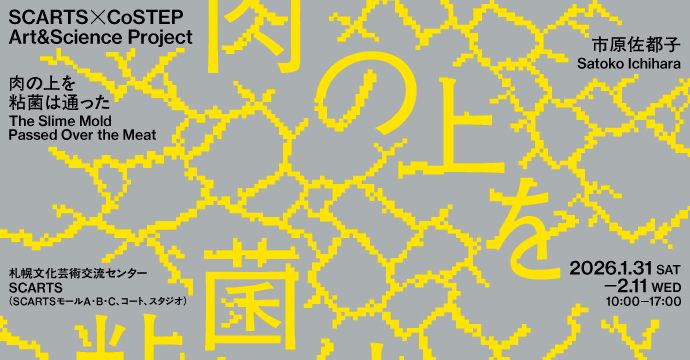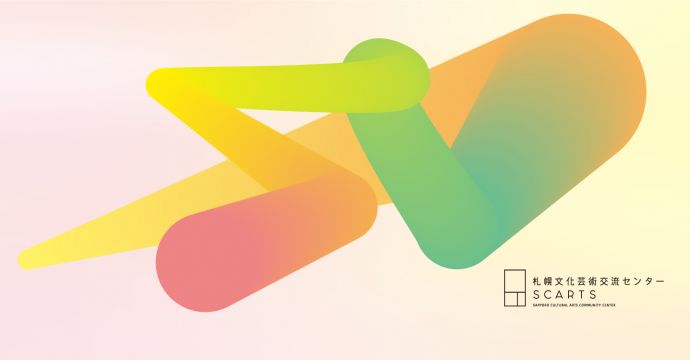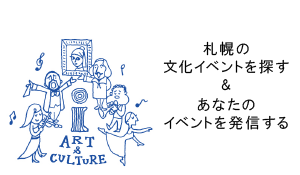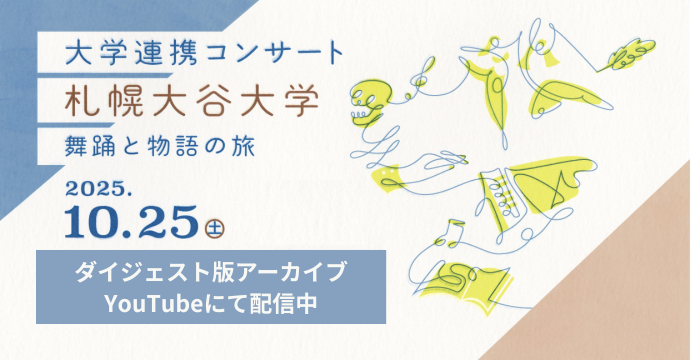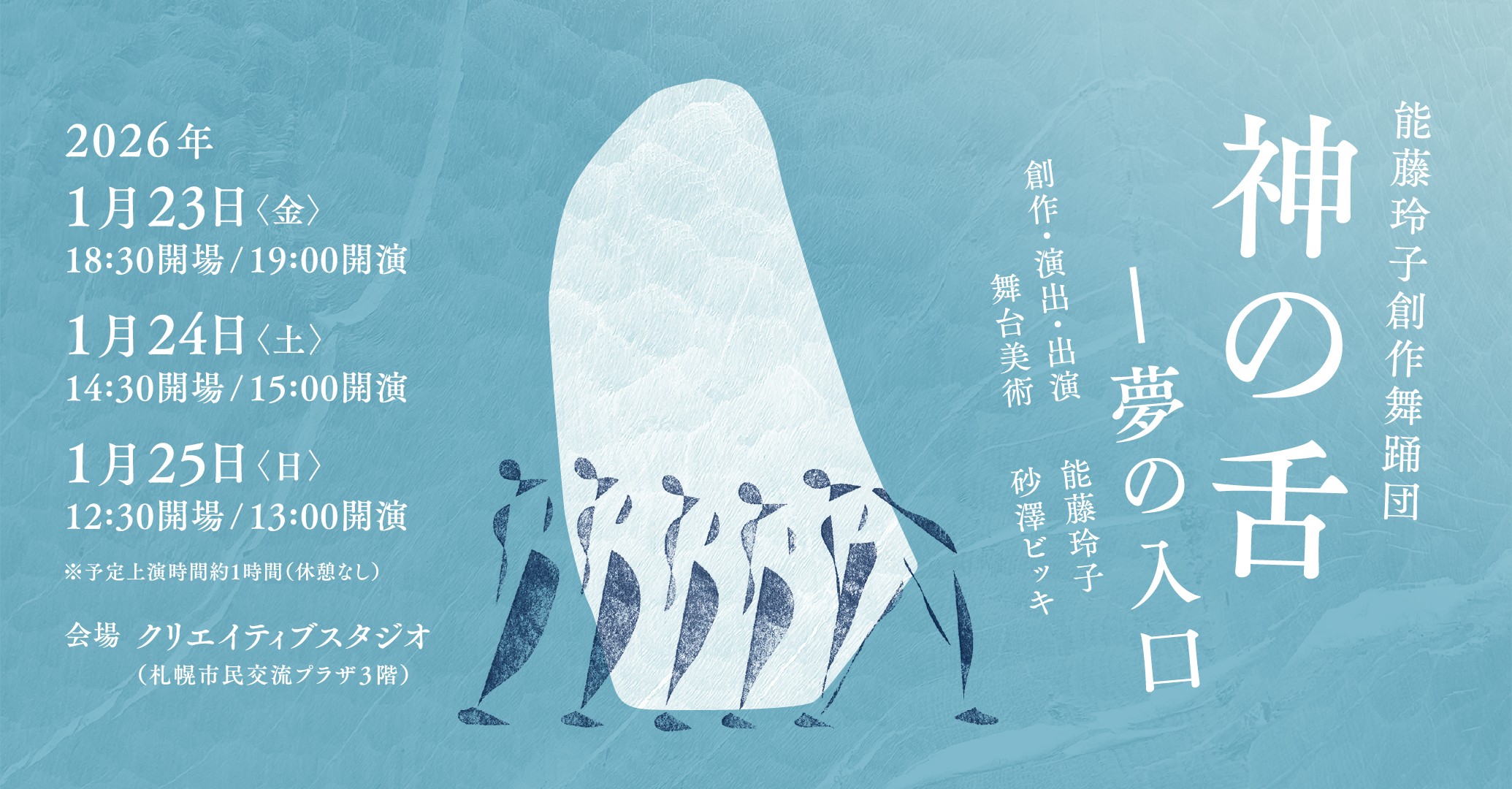本日は開館日です
開館時間 9:00~22:00
ここから本文です。
トピックス
SCARTSからのおすすめ情報
SCARTSで開催するイベント情報
-
 主催事業 美術 レクチャー 上映会 その他
主催事業 美術 レクチャー 上映会 その他 SCARTS×CoSTEPアート&サイエンスプロジェクト
札幌市立高校特別プログラム「あかさかな」2025年10月26日(日)、2025年11月15日(土)、2025年12月14日(日)、2026年2月8日(日)
-
 貸館事業 販売(物産)
貸館事業 販売(物産) リアン(絆)マルシェ
2026年1月16日(金)
-
 貸館事業 販売(物産)
貸館事業 販売(物産) Hand work マルシェ
2026年1月17日(土)
-
 貸館事業 音楽
貸館事業 音楽 竹形 貴之 クラシックギター トーク&ミニコンサート
2026年1月17日(土)
-
 貸館事業 説明会
貸館事業 説明会 ロケフォト相談会inHOKKAIDO
2026年1月18日(日)
-
 貸館事業 販売(物産)
貸館事業 販売(物産) ハッピーマーケットSappro Vol.5
2026年1月18日(日)
-
 貸館事業 販売(物産)
貸館事業 販売(物産) リアン(絆)マルシェ
2026年1月19日(月)・20日(火)
-
 貸館事業 販売(物産)
貸館事業 販売(物産) ウィッグユキ展示会
2026年1月20日(火)








お知らせ
-
2026年1月16日(金)
札幌市民交流プラザ -
2025年12月22日(月)
札幌文化芸術交流センター SCARTS -
2025年12月25日(木)
札幌市民交流プラザ -
2026年1月14日(水)
札幌市民交流プラザ