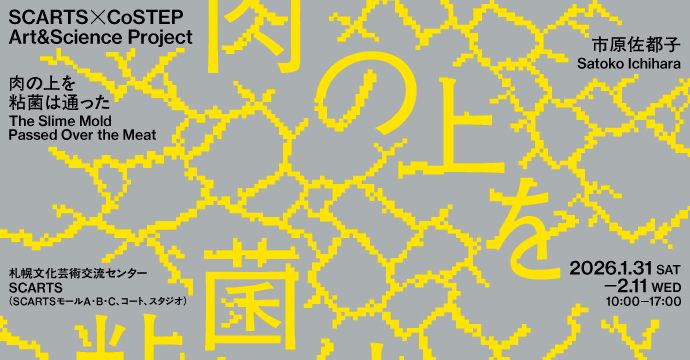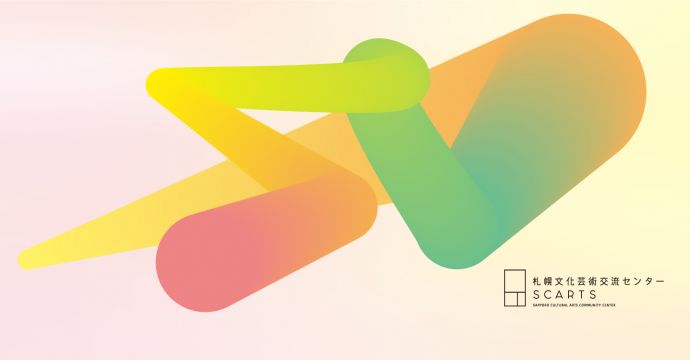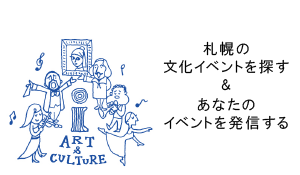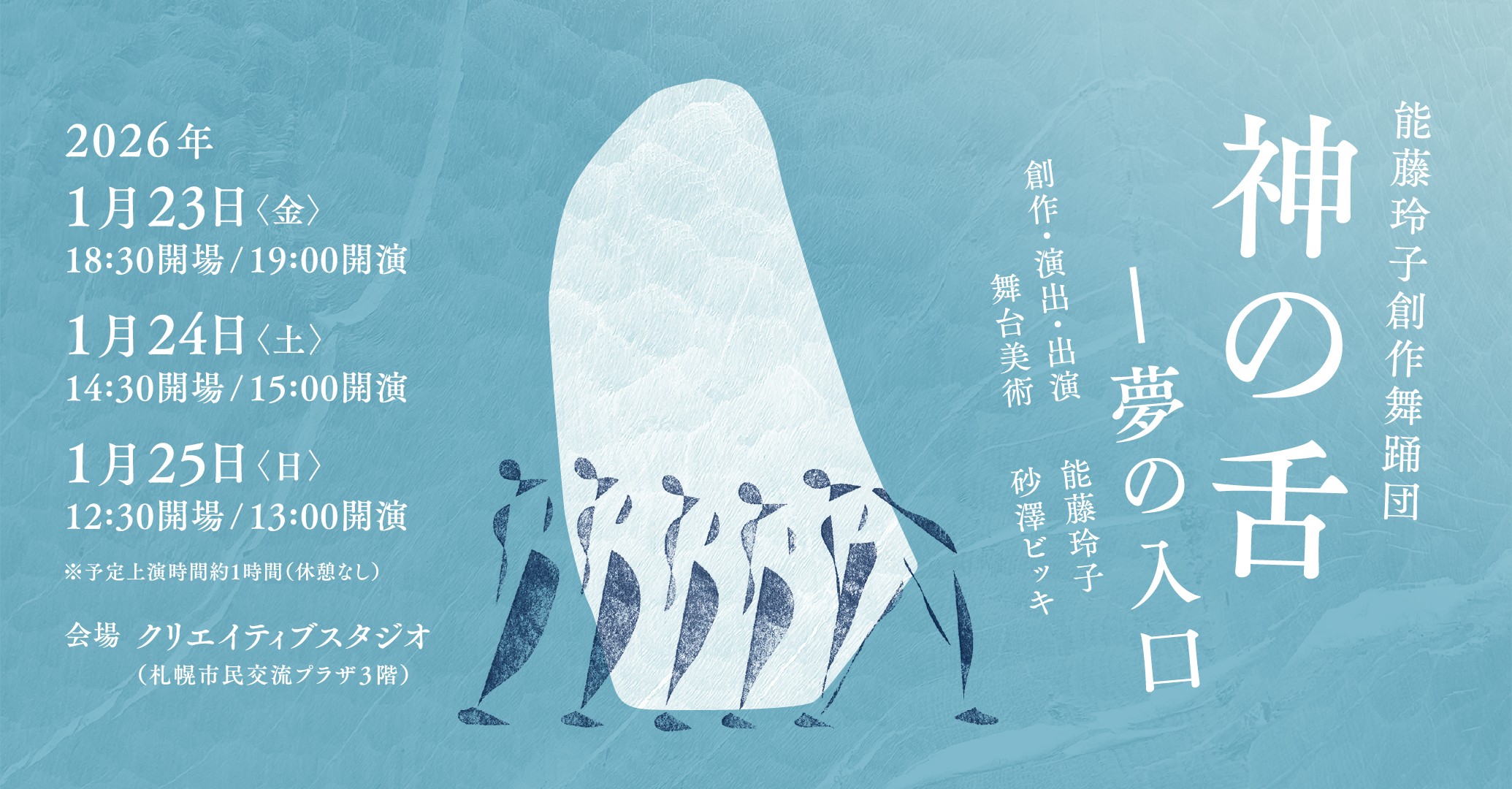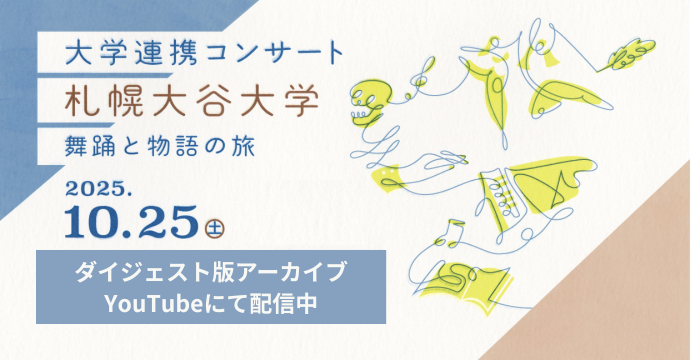本日は開館日です
開館時間 9:00~22:00
ここから本文です。
トピックス
SCARTSからのおすすめ情報
SCARTSで開催するイベント情報
-
 主催事業 美術 レクチャー 上映会 その他
主催事業 美術 レクチャー 上映会 その他 SCARTS×CoSTEPアート&サイエンスプロジェクト
札幌市立高校特別プログラム「あかさかな」2025年10月26日(日)、2025年11月15日(土)、2025年12月14日(日)、2026年2月8日(日)
-
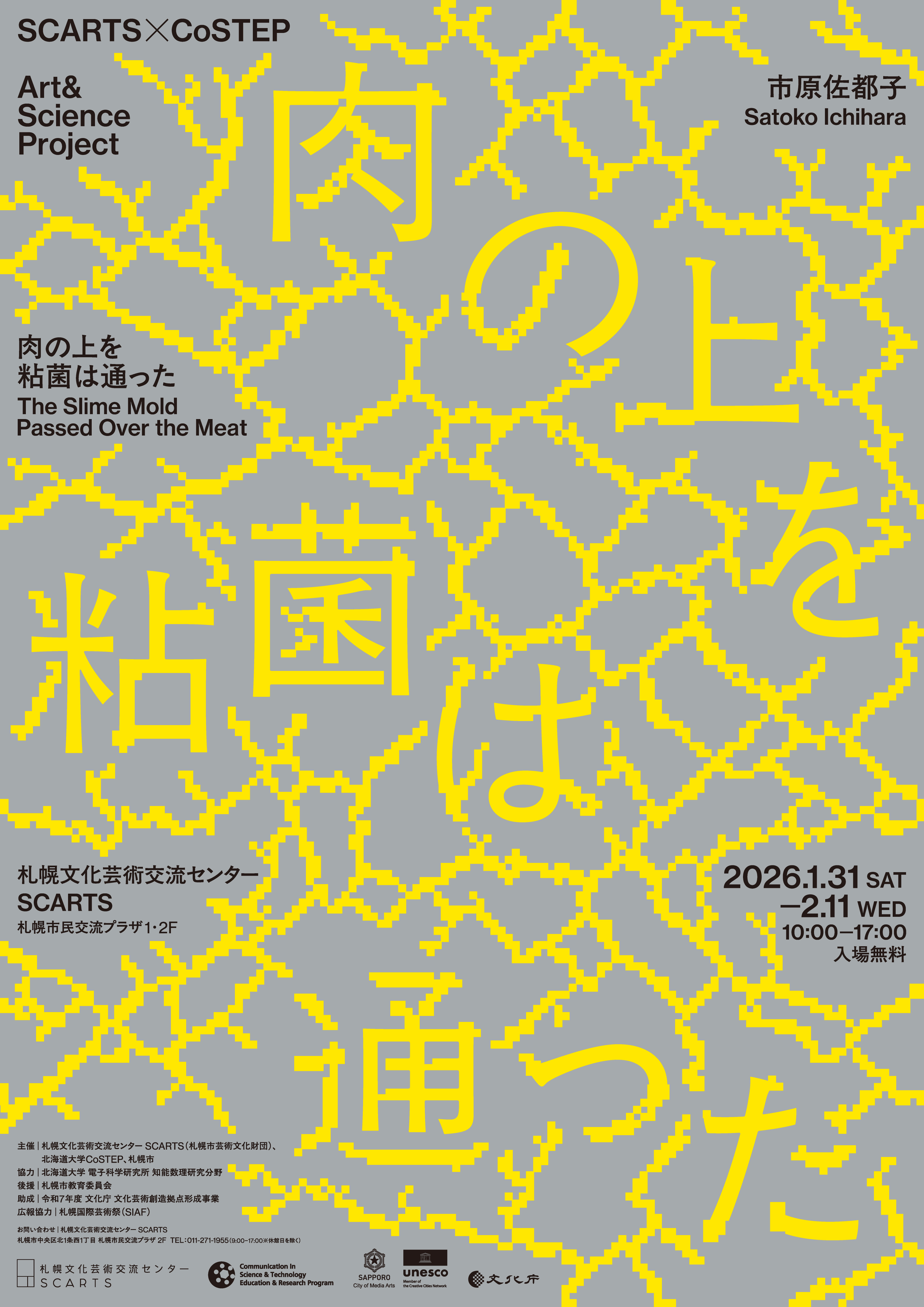 主催事業 展示 美術 トーク 上映会
主催事業 展示 美術 トーク 上映会 SCARTS×CoSTEPアート&サイエンスプロジェクト
市原佐都子『肉の上を粘菌は通った』2026年1月31日(土)~ 2月11日(水・祝)
-
 共催事業 展示 トーク
共催事業 展示 トーク 天神山、みたび、まちにいく。
2026年2月14日(土)
-
 貸館事業 その他
貸館事業 その他 朗読会 はまなす Vol.53
2026年2月16日(月)
-
 貸館事業 販売(物産)
貸館事業 販売(物産) しとらすの会・着物 ハンドメイド市
2026年2月17日(火)・18日(水)
-
 貸館事業 講演
貸館事業 講演 まち×大学 まなび交流会 第0回~地域とつくる未来、大学とひらく可能性~
2026年2月18日(水)
-
 貸館事業 講演
貸館事業 講演 フィールデイズ未来フォーラム 2026
グラスフェッドってなぁに?2026年2月20日(金)
-
 貸館事業 展示
貸館事業 展示 北海道情報大学 湯村研究室 2025年度卒業研究展
2026年2月20日(金)・21日(土)








お知らせ
-
2026年2月5日(木)
札幌市民交流プラザ -
2026年1月25日(日)
札幌文化芸術交流センター SCARTS -
2026年1月20日(火)
札幌市民交流プラザ -
2026年1月14日(水)
札幌市民交流プラザ