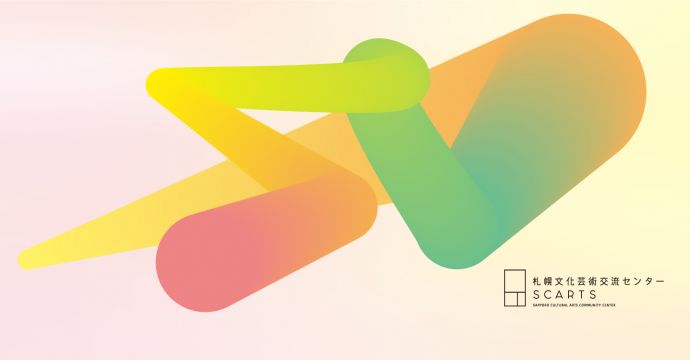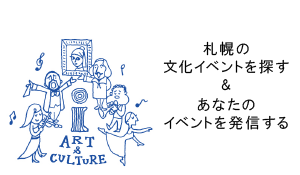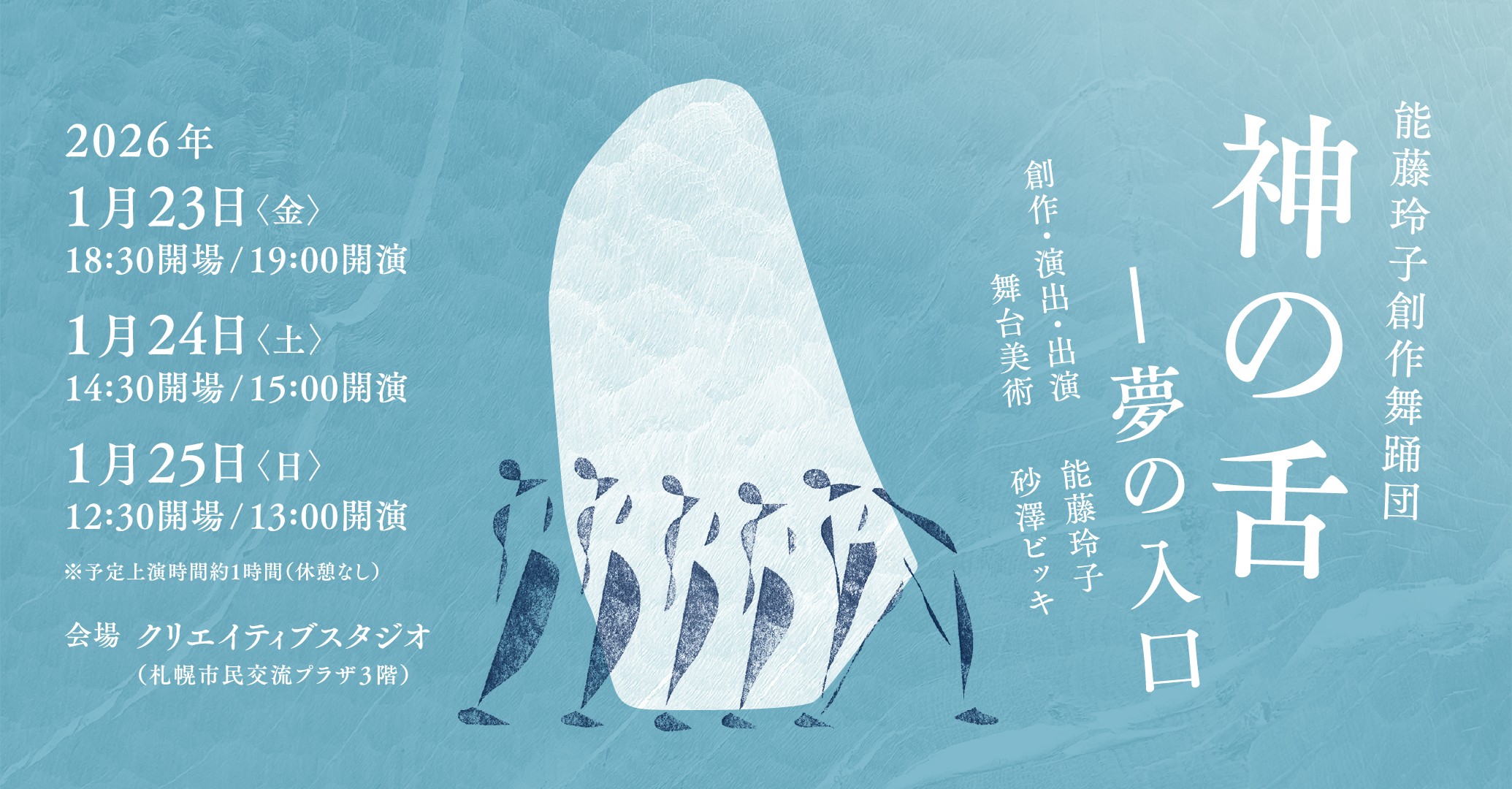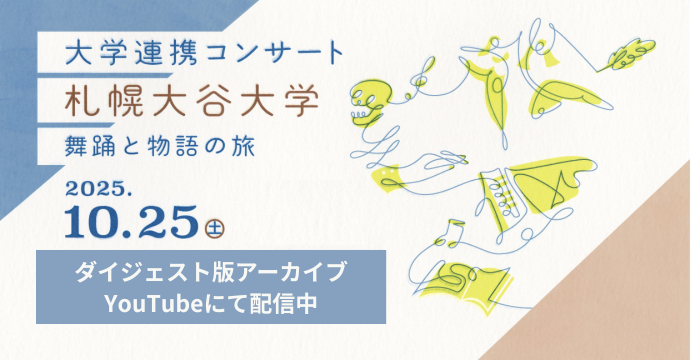本日は開館日です
開館時間 9:00~22:00
ここから本文です。
トピックス
SCARTSからのおすすめ情報
SCARTSで開催するイベント情報
-
 貸館事業 販売(物産)
貸館事業 販売(物産) リアン(絆)マルシェ
2026年2月26日(木)~ 28日(土)
-
 貸館事業 販売(物産)
貸館事業 販売(物産) しとらすの会・着物 ハンドメイド市
2026年2月27日(金)・28日(土)
-
 貸館事業 販売(物産) その他
貸館事業 販売(物産) その他 スピリチュアルマルシェ カムイの風が吹くとき
2026年2月28日(土)
-
 貸館事業 音楽
貸館事業 音楽 ~フルートとともに~ スプリングコンサート
2026年2月28日(土)
-
 貸館事業 講演
貸館事業 講演 60分でまるわかり!新NISAで活用できる資産形成・資産運用の考え方セミナー
2026年2月28日(土)
-
 貸館事業 販売(物産)
貸館事業 販売(物産) 国際女性day ミモザの日マルシェ
2026年3月1日(日)
-
 貸館事業 展示 販売(物産)
貸館事業 展示 販売(物産) 足と靴のお悩み相談会
2026年3月2日(月)・3日(火)
-
 貸館事業 販売(物産)
貸館事業 販売(物産) リアン(絆)マルシェ
2026年3月2日(月)・3日(火)








お知らせ
-
2026年2月5日(木)
札幌市民交流プラザ -
2026年1月25日(日)
札幌文化芸術交流センター SCARTS -
2026年1月20日(火)
札幌市民交流プラザ -
2026年1月14日(水)
札幌市民交流プラザ